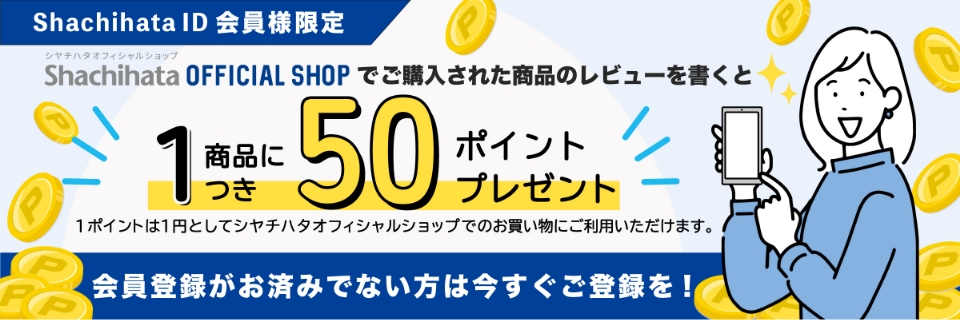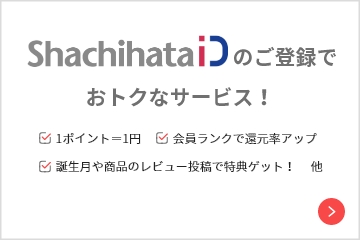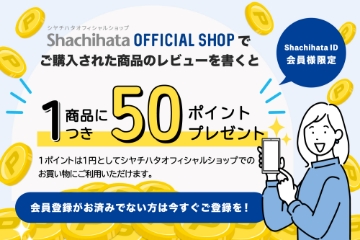七夕飾りの意味と定番からおしゃれな作り方を紹介!


保育園・幼稚園に通う小さなお子さまがいるご家庭では、伝統行事・七夕に笹飾りをする方も多いでしょう。しかし、ご家庭で準備するときはできるだけ手間のかからない方法で七夕飾りを作れると嬉しいですよね。
そこでこの記事では、折り紙と最低限の道具があれば簡単に作れる七夕飾りの制作方法をご紹介します。さらにひと工夫したおしゃれな七夕飾りの作り方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
七夕笹飾り(笹飾り)の意味

七夕飾りは、短冊に願いごとを書いて笹の葉に飾るのが定番です。しかし、それ以外にも笹にさまざまな飾りつけをしているのをご存じでしょうか。七夕飾りには、それぞれ意味があります。飾りの意味を知って、もっと七夕を楽しみましょう。
短冊の意味
短冊には「学問や書道の上達」の意味があります。古くから続く七夕は、機織りや裁縫・書道・学問の上達を願う行事としておこなわれていました。現在では自分の叶えたい願いごとを書くことが多いですが、本来であれば物欲を叶えるような願いよりも、手習いごとなどの上達を願うほうが良いとされています。
とはいえ、七夕の願いごとは自由であるべきです。家族の健康や、合格祈願・恋愛成就などの叶えたい夢や願いを、自由に短冊に書きましょう。

吹き流しの意味
吹き流しは昔の織糸を垂らした形をあらわしており、機織りが上手だった織姫を象徴するアイテムです。元々は手芸や機織りの上達を願って飾られていました。現在では大きなくす玉に吹き流しを付けるのが定番となっています。
短冊と同じ五色が使われており、それぞれの色は陰陽五行説の考えに由来しています。それぞれの色が持つ意味は以下の通りです。
- 青:人間力を高める
- 赤:祖先や親に感謝する
- 黄:人を大切に思う
- 白:ルールを守る
- 黒:学業向上
くずかごの意味
七夕飾りをつくるときに出た紙くずを入れて飾るくずかごには、「清潔」「倹約」「整理整頓」などの心を育てる意味があります。くずかごと投網(網飾り)はよく似ており、作り方も同じですが、それぞれ持つ意味が異なります。できれば、別々に作って飾りましょう。
清潔や整理整頓の意味合いがあるため、「子どもが自分でしっかりと整理整頓できるように」「散らかりがちな家をきれいにできるように」などの願いを込めて、くずかごを飾ってみてはいかがでしょうか。
網飾りの意味
網飾りは漁で使う網をあらわしており、「豊作・大漁」「食べるものに困らないように」などの願いが込められています。また、網で魚をすくって引き寄せることから「幸せを引き寄せる」と言う意味合いもあるといわれています。
網飾りは、細かな切れ目が美しく、漁で使う網のほかに天の川を模しているともいわれています。星や月のモチーフを飾りつけて楽しむのも良いでしょう。
折り鶴の意味
昔から長寿の象徴とされている鶴は、折り紙の定番です。千羽鶴は平和の象徴としても知られています。七夕の飾りとして折った鶴は長寿や家内安全を願って飾られます。
折り紙に詳しくない人でも「鶴だけは折れる」という人も多いはずです。子どもと一緒に鶴を折ると、折り方を通して教わる心や教える心が育まれます。家内安全や健康長寿を願いながら、年齢の数だけ、もしくは最年長の年齢の数だけ鶴を折りましょう。
紙衣(かみこ)の意味
紙衣(かみこ)は、和紙で着物の形に折ります。和紙で作られた着物は、裁縫の上達を願うとともに、自分や家族に降りかかる災いや病の身代わりになってくれる飾りです。そして、生涯着る服に困らないようにという願いもあります。
さらに紙衣(かみこ)には、子どもが無事に育つように身代わりに流す形代(かたしろ)としての意味も込められています。
自分の好きな色の折り紙を使って、家族や大切な人を思いながら紙衣を折ってみましょう。
巾着の意味
巾着は商売繁盛や金銭に不自由しないことを願う飾りです。折り紙を巾着や財布の形に折って飾り、金運上昇や貯蓄が増えることを願いましょう。
無駄遣いを防ぐために、巾着の口はしっかりと閉じておくことが大切です。また、地域によっては本物の財布を飾るところもあるようです。
巾着をつくるときは、好きな色の折り紙を使いましょう。金運上昇を願うのであれば、黄色や金色、白、グリーンなどの運気を上げる色がおすすめです。
折り紙だけで簡単!定番の七夕飾りの製作方法

次に、折り紙を折るだけで簡単に作れる定番の七夕飾りを6つご紹介します。制作方法もあわせてお伝えしますので、ご家庭でもぜひ作ってみましょう。
短冊
七夕でおなじみの、願いを書いて吊るす短冊です。折り紙を長方形にカットするだけという簡単な作業工程ですので、どんな方でも気軽にチャレンジできますよ。

吹き流し
吹き流しとは、紙風船やくす玉、輪などにカラフルにたなびく紙を貼り付けたものです。織姫に備えられた5色の織り糸を表し、裁縫の上達を願って飾ります。
【作り方】
- 折り紙を縦方向に3〜4回山折りしてから開く
- 上部を2cmほど残し、ついた折り線に沿って切る
- 2をくるっと巻き、端をのりかテープで留める
提灯(ちょうちん)
提灯は、心を照らす灯としての意味合いを持つ笹飾りです。複雑な構造に見えますが、意外と簡単に作れます。切り方によってフォルムが変わるため、お子さまと一緒にいろんな形を作ってみるのも楽しいですよ。
【作り方】
- 折り紙を長方形になるよう山折りする
- 折り目と反対側を約1cm幅に折る
- 折り目の上から1cmほどの等間隔に切り込みを入れる
- 山折りを開き、端をのりかテープで貼り付ける
貝飾り
貝飾りは海の恵みを表す笹飾りであり、古くから大漁祈願として飾られてきました。らせん状の凝った見た目をしていますが、複雑な工程は一切ありません。
【作り方】
- 折り紙を長方形になるよう山折りする
- 折り目に対して垂直方向に直線の切り込みを入れる
- 山折りを開き、切り込みが縦になる向きで持つ
- 上下の対角をひねりながら合わせ、のりかテープで留める
あみ飾り
網飾りは、漁に使う網を模し、大漁を願って飾ります。手作りするときは、切れ込みの間隔を変えたり、さまざまな色の折り紙を貼り合わせたりするのもおしゃれです。
【作り方】
- 折り紙を細長い長方形になるよう2回山折りする
- 折り目に対して垂直方向に1cm程度の等間隔で切り込みを入れる
- 反対側の開いている方向から2で入れた切り込みの間を等間隔で切る
- 山折りをすべて広げる
輪つなぎ
輪つなぎは、星が連なる天の川と人とのつながりや、夢・目標に到達するまでの道のりを表しています。パーティーの輪飾りとしてもよく用いられており、初心者にも易しい作り方の笹飾りです。
【作り方】
- 折り紙を2〜3cm程度の幅に細長く切る
- 1本の端を貼り付けて輪を作る
- もう1本の紙を2で作った輪に通し、端を貼り付けて輪にする
- 3の工程を繰り返し、鎖のように連ねていく
折り紙にひと工夫!おしゃれな七夕飾りの作り方

おしゃれな七夕の笹飾りを作りたいときは、折り紙にひと工夫を加えてみましょう。以下では、ワンランク上に見える笹飾りをピックアップし、その作り方をご説明します。工夫を要するとはいえ、未就学児や小さなお子さまでも問題ない程度の難易度ですので、折り紙工作に苦手意識がある方もぜひチャレンジしてみてくださいね。
菱飾り
三角が連なった形をしている菱飾りは、前の章で説明した輪つなぎと同じく天の川を表す笹飾りです。かわいい見た目に反して、とても簡単に作れます。
【作り方】
- 折り紙を3色以上用意する
- それぞれ三角もしくは四角にカットする
- てっぺんの角が少し重なるようにして貼り付けていく
天の川
七夕ならではのモチーフといえば天の川ですよね。あみ飾りをアレンジすれば、天の川も簡単に作れます。
【作り方】
- 大きめのあみ飾りを作る
- 端をそっとひっぱって広げる
- 星の形に切った折り紙をバランスのよい配置になるようにのりで貼り付ける
星飾り
星飾りは、願い事が天まで届くよう祈りが込められた笹飾りです。さまざまな折り方で作れますが、ここでは紙とハサミだけで作れる簡単な作り方をご紹介します。大・小さまざまなサイズの星を作り、輪つなぎのようにアレンジするのもおしゃれですよ。
【作り方】
- 折り紙を縦の長さが20〜25cmくらいになるように細長くカットする
- それぞれ1〜2cm程度の幅になるよう山折り・谷折りを10回繰り返してじゃばら状にする
- 余った部分は切って長さを調節する
- 星型になるよう形を整え、端をのりで貼り付ける
織姫と彦星
七夕の象徴の織姫・彦星。お飾りとして作れば、笹が華やかな仕上がりになりますよ。作り方は複数ありますが、今回はその中でも最も簡単なトイレットペーパーの芯を活用した立体的な織姫・彦星を作る方法をお伝えします。
【作り方】
- 2本のトイレットペーパーの芯それぞれにきれいな柄の折り紙を巻きつけてボディを作る
- 別の紙で織姫と彦星の顔を作る(絵を書いてもOK)
- 顔をボディに貼り付ける
折り紙とはさみで手軽にかわいい七夕飾りを作ろう!

伝統行事・七夕で定番の笹飾り製作は、指先を多く使う作業ですので、小さなお子さまと一緒に取り組む遊びの一環としてもおすすめです。今回の記事でご紹介したアイデアをいくつか組み合わせて、豪華な七夕飾りを作ってみましょう。
折り紙を準備するときは、ぜひはさみが不要な「おりがみ工場」をご活用くださいね。


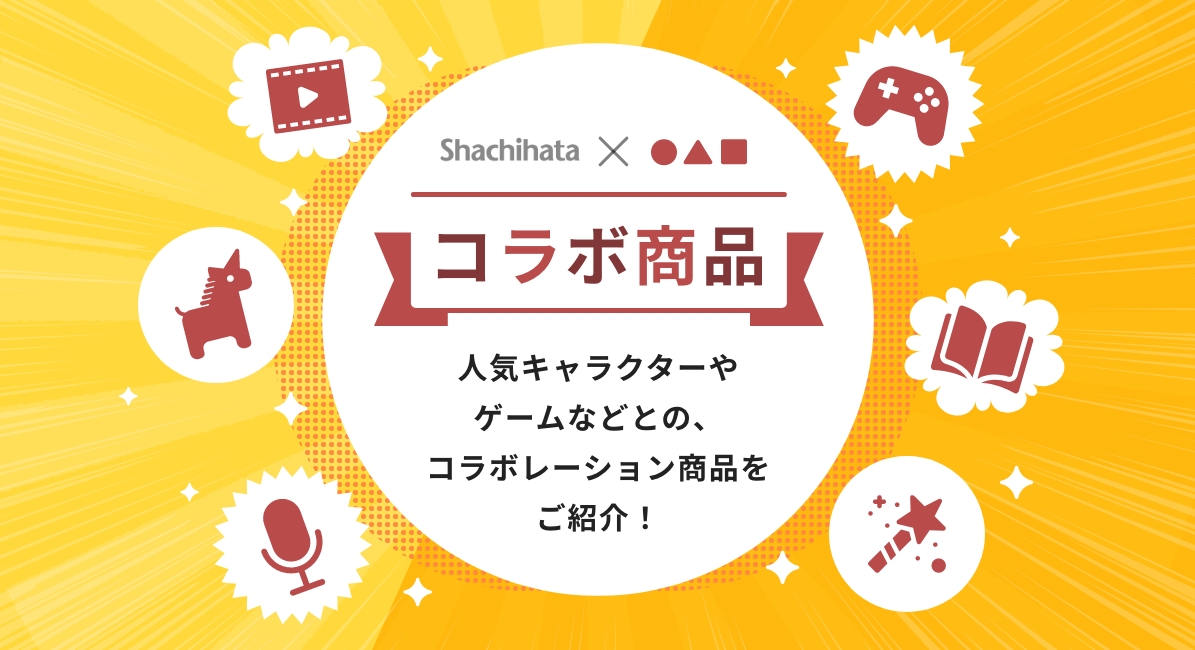



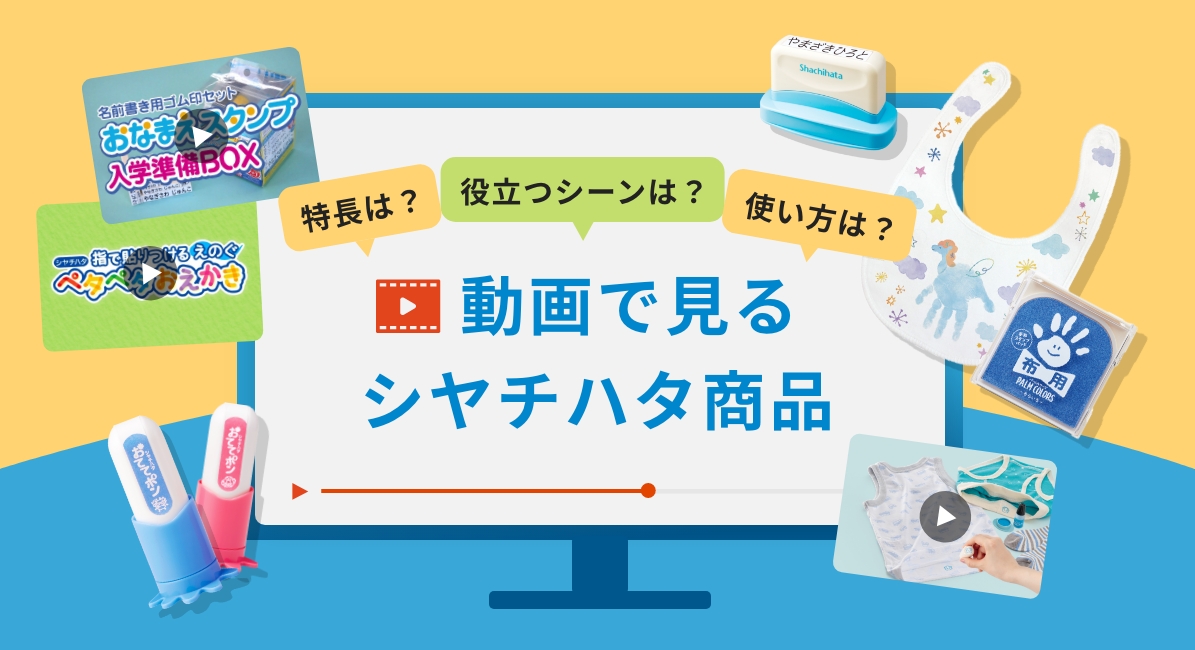



























1-1024x682-1-600x400.jpg)